
「生きる」を、つなぐ新しい酪農のカタチ
~「経営×DX」が、日本の酪農の進化を促す~
株式会社ファームノートホールディングス
代表取締役 小林晋也氏
日本の酪農・畜産業は課題が山積している。食料自給率の低さ(カロリーベースで13%)、業界における平均給与の低さ、酪農・畜産業従事者の減少・高齢化など、食料安全保障が脅かされている状況にある。こうした課題を解決することが、日本の酪農・畜産業の持続的発展のためには不可欠だ。各方面で多彩な取り組みが進められているが、北海道・帯広で牧場経営の効率化・高収益化を目指し、酪農・畜産向けDX・IoTソリューションを提供している企業が、株式会社ファームノートホールディングス(以下、ファームノート)である。創業者である、代表取締役の小林晋也氏にお話を伺った。
困っている人を助けたいという
シンプルな気持ちが創業の原点
ファームノート立ち上げに至った経緯をお聞かせください。日本の酪農・畜産業についてどのような問題意識があったのでしょうか。
起業のきっかけは、酪農家からの問い合わせでした。「酪農の世界はIT化が非常に遅れている。何とかして欲しい」と。そこで実際に現場に行くと、紙の台帳で牛群を管理しており、デジタル化はまったく進んでいない。さらに調べていくと、酪農業界には「経営者」が少ない、「経営」そのものがないことに気付きました。もちろん酪農家は牧場を経営しますが、一般企業のように経営の意思決定やメカニズムが働いていないのです。衝撃的でした。このままでは酪農家に明るい未来はない、何とかしなければと思い、DXによって酪農家を支援すべくファームノートを立ち上げました。ただ、私には元々酪農に対する想いがあったわけではなく、業界の抱える問題に意識的だったわけでもありません。人が苦しんでいる、困っている、それならばその人を助けたいという率直な気持ちが、ファームノート起業の原点です。縁に導かれて、今ここにいると思っています。
人を助けたいという気持ちが、グループビジョンである「『生きる』を、つなぐ。」に込められているのでしょうか。
「『生きる』を、つなぐ。」ために、次世代の自然や環境、生命、人間が豊かに持続する世界を革新的な技術で創り上げていくことをビジョンとして掲げました。そこには、コンピューティングを通じて、人や動物、自然の豊かさに貢献したいという想いがあります。その大前提にあるのは、すべてはつながっているということです。持続的な社会を創るには、人と人のつながりを大切にして、お互いを尊重し、感謝を忘れずに行動する必要があります。シンプルに困っている人がいれば助ける、苦しんでいる人に寄り添う、いわば慈悲の精神が、「生きる」をつないでいくと思いますし、私の経営のコアにあります。
生産性・収益性の向上を目指した
DX・IoTソリューションの導入
日本の酪農には「経営」そのものがないと指摘されましたが、それによって浮かび上がった課題は何でしょうか。
あらゆる企業において経営が目指すのは、収益の向上です。酪農業において収益を上げる手段は、生産性を上げることに尽きます。日本の酪農の生産性の低さは世界と比べても明白で、たとえば個体乳量で、欧米は日本の約1.5倍の生産性を達成しています。したがって私たちが提供するDX・IoTソリューションも、生産性向上に向けたものになります。プロダクトは次の5つ。「Farmnote Cloud」は牛の収穫乳量や投薬・処置歴等の情報を個体ごとに紐づけて集積管理し、牛の状態や管理計画等を一元管理し共有するツール。スマホで扱えることから、高いユーザビリティを実現しています。約2,000の酪農・畜産家に導入、約38万頭を管理しています。「Farmnote Color」は、牛の行動・情報を取得し、AIにより分析・可視化するウェアラブルデバイスで、約10万頭の牛に装着されています。「Farmnote Gene」は牛の遺伝子サンプルを採取し、収益貢献度を乳量や繁殖性、疾病耐性等に基づいた総合指標で数値化し、後継牛選定をサポート。国内40%のシェアを確保しています。新たに着手した「ジェネティクスサービス」は和牛とホルスタインの受精卵を販売するサービス。非後継牛に受精卵を移植することで、酪農家の収益アップをサポートします。生まれた和牛子牛は高値での販売が可能となります。これらDX化とゲノム技術の導入によってもたらされる生産性向上が、酪農家が抱える多くの課題解決に確実につながっていきます。さらには経営コンサルティングサービスとして「Farmnote Compass」を提供しています。
それらDX・IoTソリューションは、貴社独自のサービスなのでしょうか。また酪農家の反応はいかがでしょうか。
個々の商品・サービスは、すでに単体で市場に供給されていたもので、私たちが先駆けて行ったものではありません。しかし、それぞれのソリューションをインテグレーションし、複合的な価値を生み出すことが私たちの強みです。私たちのソリューションは、導入して終わりではありません。むやみに拡販するのではなく、正しく運用して生産性向上に結び付けていく必要がある。理解してもらった人が、次の理解者を生んでいく、その連鎖を通じてDX化を拡大させていきたいと考えています。


「牧場を、手のひらに。」をコンセプトにスマートフォンで牛群管理ができるアプリ「Farmnote Cloud」
(写真提供:ファームノート)
みんなで知恵を出し合って
世の中を良くしていきたい
2019年に設立した自社牧場・ファームノートデーリィプラットフォームで行われているインテグレーション事業について教えてください。
自社プロダクトの実証実験の場として、そして本業として中標津、遠軽をはじめ5つの牧場経営を行っています。自ら生産者となることで酪農・畜産業界のDX化を加速させていきたいと考え、2019年に創業しました。自社保有の牛約700頭、運営受託の牛約800頭を飼育。オペレーションの徹底した自動化・標準化と自社のDX・ゲノムプロダクトを導入することで、高い生産性を実現しています。たとえば平均個体乳量では、一頭当たりの国内平均が29kg/日であるのに対し、38kg/日まで引き上げました。他にもゲノム検査によるトータルバランス指標で牛を選別し、牛群能力(牛の生涯収益)向上も実現しています。近い将来、自社牧場を高収益牧場のモデルとして外部展開したいと考えています。
2023年から2024年に実施された資金調達では、DBJからの資金供給も受けていますが、その目的を教えてください。
今回の資金調達は、新たに着手した事業である「ジェネティクスサービス」、「Farmnote Gene」、育種改良事業の拡大・強化が大きな目的です。受精卵は外部事業者からの仕入れに加え、顧客の要望に基づいたオーダーメイドの受精卵製造も推進していきます。またクロスセルを推進するため、抜本的な構造転換を図りたいと考えています。資金調達では、DBJさんに前向きに取り組んでいただきました。それが他からの資金調達がスムーズにいった背景にあると思います。あるとき、居酒屋でDBJの職員の方をお見掛けしたことがあり、熱く議論を交わす様子に圧倒されました。その熱量で、今後もパートナーとして、日本の新しい酪農の世界を一緒に作っていただきたいと思っています。
今後の展望についてお聞かせください。
数年後のIPOを見据えています。それは上場によって資本効率を向上させ、食料問題のみならず、様々な社会課題に向き合う会社を増やしたいからです。ただ、「社会問題を解決する」と、大上段に振りかざして肩肘張るのではなく、みんなの知恵を出し合って世の中をより良くしていきたい。そのためにも人材育成は自身のミッションの一つと考えています。人が成長すれば、そこから新たな技術や革新が生まれます。ファームノートがそのことを実証しています。縁を大切にし、感謝に溢れ、問題の本質と向き合う、そんなリーダーを育てたいと思っています。
小林晋也氏
KOBAYASHI Shinya
代表取締役
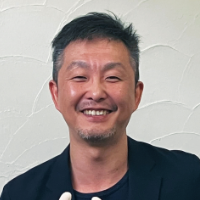
この記事は季刊DBJ No.55に掲載されています
季刊DBJ No.55
