
世界に誇れる再生事業を、福島県から
~独自技術で資源の循環に貢献する地域密着型企業~
株式会社アサカ理研
代表取締役社長 山田浩太 氏
持続可能な社会の実現が課題となる現在、資源を無駄にするのではなく循環させるサーキュラーエコノミー(循環型経済)の考え方が注目されている。その実現に欠かせないピースである「資源の再生」の必要性にいち早く目をつけ、1969年の創業以来独自の技術を磨いてきた企業が福島県に本拠を置く株式会社アサカ理研だ。これまで都市鉱山から有価金属の回収・再生を行う貴金属事業や、地球環境保全に貢献する環境事業などでニッチ・トップの企業として注目を浴びてきた同社は、2019年から脱炭素社会の実現に欠かせない「リチウムイオン電池の再生」への挑戦も開始した。同社を率いる代表取締役社長の山田浩太氏にお話を伺った。
父から受け継いだ経営のバトンと
社員のビジョンを尊重する理念
アサカ理研は、1969年にプリント基板屑およびエッチング廃液の新液への再生目的として設立されました。そして現在も、エッチング廃液再生や都市鉱山からの有価金属回収など、環境保全や資源の循環を目的とした事業を営まれています。
創業当時はまだ社会に浸透していなかった言葉ですが、当社は半世紀以上にわたり「リサイクル」を中核としてきた会社だと言えるでしょう。創業者は私の祖父で、鉄鋼加工品の工場に勤める中で、排出される廃液が環境に悪影響をおよぼし、価値ある資源が活用されずに失われていく様を目の当たりにし、「これは将来、必ず問題になる」と考え、自ら考案した解決策を社会に届けるべく会社を立ち上げたと聞いています。そうした祖父の姿勢にも表れているように、当社では何かを必要と感じたとき、その時にある技術や環境を使って「小さくてもいいから、とにかく試してみる」カルチャーが根づいています。当社ではこれを、ありあわせの材料で掘っ立て小屋を建てることにたとえて「バラック思考」と呼んでいます。この思考のもとで積み重ねてきた試行錯誤が、成膜装置から母体を傷めずに狙った貴金属だけを回収する「選択的剥離」と呼ばれる特殊な化学処理によって対象の貴金属と不純物を分離し、精製・高純度化を図るといった、当社独自のコア技術に結実しています。
創業者であるお祖父様、そしてお父様がつないできたアサカ理研の経営のバトンを、2022年に受け継がれました。
社長に就任してから常に思っているのは、父・慶太が大切にしてきた「豊かな創造性を発揮し、社会貢献を果たす」という社是を、これからも大切にしていきたいということです。自分を育ててくれた父への恩返しをしたいという気持ちもあり、それこそが私が社長になる意味だと感じていました。父から直接、「こういう経営をせよ」と言われたことはありませんが、その背中を見続ける中で、社是を実現するための鍵は「社員のビジョンを尊重し、ともに事業を育てていくこと」にあると気づきました。実際、私が新入社員としてアサカ理研に入社した当初、会社をより良くするための方策を語り合う社員の集いに参加した際、多くの社員が熱意をもって自身の考えを語る姿に大きな衝撃を受けました。そんな社員たちの存在こそが、当社の財産であることを父も認識していたのだと思いますし、なにより、人は自分のビジョンが実現に近づいていると感じるときにこそ、最もやりがいを感じ、創造的になれるーーそれが父の理念であり、当社で働くうちに私自身の確信にもなりました。だからこそ、社長として先頭に立って会社を引っ張るのではなく、社員の「やりたいこと」を尊重し、社員一人ひとりの想いを束ねて、当社の独創的な技術と事業をさらに伸ばしていく環境づくりに努めていくことこそ、自分の使命だと感じています。
リチウムイオン電池の再生事業を通じて
地球温暖化対策、地域活性化に貢献
独創性を発揮する新たな分野として、2019年にリチウムイオン電池(以下、LiB)の再生事業に参入されていますね。
いま世界中で地球温暖化対策が急務となる中、自動車産業ではEV(電気自動車)へのシフトが加速しています。この潮流は、自動車を基幹産業とする日本経済の行方を左右しかねない重要な変化ですが、日本にはEV製造における大きな弱点があります。それは、EVに不可欠なバッテリー、すなわちLiBの原料となるレアメタル(希少金属)を海外からの輸入に依存しており、製造コストが高くなりやすいという点です。そこで、廃棄されたLiBからリチウム、コバルト、ニッケル、マンガンといったレアメタルを回収・再生し、再び製造現場に原料として供給する「LiB to LiB(水平リサイクル)」を実現することが、日本のEV製造の競争力を高めるうえで不可欠となっています。ただし、LiBには様々な素材が複雑に組み合わされており、個別に分離することが難しい一方で、バッテリー製造には極めて高い純度の材料が求められるため、その再生は非常に難しいとされてきました。そんな中、選択的剥離や分離・精製といった分野で独自のノウハウを培ってきた当社であれば、レアメタルの高回収率を実現できると判断し、事業化に踏み切ったのです。加えて、当社の溶媒抽出法を応用すれば、一般的なレアメタルの回収に伴う焼却工程を必要とせず、CO2排出の抑制も可能です。もっとも、LiB to LiBの要である使用済みLiBの再生市場は、まだ十分に成長しておらず、現時点ではビジネスモデルが確立されていないのも事実。そのため、大手企業もLiB再生事業への投資・参入には慎重な姿勢を見せています。そこで当社は、ニッチな市場でも勝負できる中小企業の特性を活かし、将来大量に発生することが予想される使用済みLiBの再生事業の開始に向けた準備を進めつつ、まずは、LiBを扱う企業の限られた製造工程で発生する工程廃材の再生に的を絞り、早期の事業化を目指すことにしました。そうすることで、資金力や人材などの面で優位な大手企業に対しても、ノウハウや技術の蓄積という形で先行者メリットを獲得できるからです。日本経済の発展、そして地球温暖化の解決に貢献できるこの事業は、当社の社員にさらなる誇りとやりがいをもたらし、一層創造性を引き出す原動力になるという期待もあります。
LiB再生事業の重要な起点として、福島県いわき市に再生工場を建設中ですね。LiB to LiBを実現する先駆けとなる取り組みを応援すべく、DBJは地域金融機関とシンジケート・ローンを組成し、アサカ理研のいわき工場建設を金融面から支援しました。
当社が実際にLiB再生事業を行う拠点が、いわき工場です。当社は2024年にトヨタ自動車とパナソニックホールディングスが出資する電池会社プライムプラネットエナジー&ソリューションズ(PPES)との間で、同社の車載用バッテリー製造工程で生まれる廃材の一部をいわき工場で再生する事業に関する覚書を締結しました。まず2026年10月に試験稼働を開始し、認証取得のためのサンプルづくりに着手します。その後2028年4月に本格稼働し、PPES工場で生じた工程廃材から再生したレアメタルを原料としてPPESの製造ラインに戻し、再び活用してもらうという循環型モデルを構築する計画です。工程廃材に特化しているとはいえ、2028年時点でLiB to LiBの実現を具体的に掲げているのは、少なくとも国内では当社のいわき工場だけです。
いわき市に工場を建てる理由の一つに、東日本大震災で被害を受けた同地域の復興の一助とする意向もあると伺いました。
私もそうですが、当社の社員の多くは福島県出身です。会社を支える社員が暮らす地域社会こそが、アサカ理研の土台そのものだと考えています。これまで受けた恩に報いたいという思いもありますし、地域の活性化なくして当社の成長はあり得ません。そして、地域社会に対する当社の最も重要な役割の一つが、雇用の創出です。その意味でも、LiB再生事業には大きな期待を寄せています。特に同事業は、地球温暖化対策や日本経済の発展に資する意義のある取り組みであり、その理念に共感し、当社で働くために全国から福島県へ移住してくる人も増えています。当社の事業が雇用を生み、地域社会が活性化し、それがさらに事業の発展、そして持続可能な社会の実現につながる― 。そんなポジティブなエコシステムを築いていくためにも、LiB再生事業を着実に育てていきたいと考えています。

LiB to LiB実現の先駆けとなるアサカ理研のいわき工場は、2028年4月の本格稼働を予定している
(写真提供:株式会社アサカ理研)

希少資源を再び活用できるようにする独自の再生技術は、サーキュラーエコノミー(循環型経済)の実現においても重要だ
(写真提供:株式会社アサカ理研)
山田 浩太 氏
YAMADA Kota
代表取締役社長
2012年に入社。経営企画や海外子会社においてマネジメント業務に従事し、2022年に代表取締役社長に就任。これまで培った企業経営と人材マネジメントに関する豊富な知識、優れたリーダーシップを発揮し、持続的な企業価値向上と経営体制の強化を牽引している。
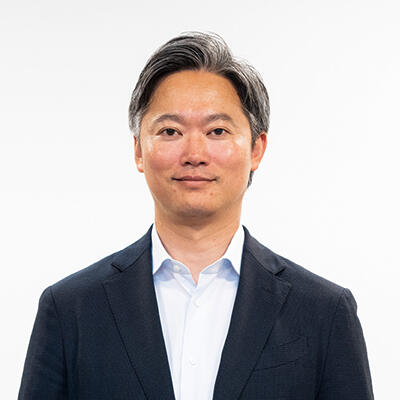
この記事は季刊DBJ No.57に掲載されています
季刊DBJ No.57
