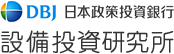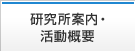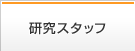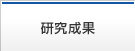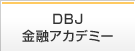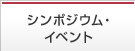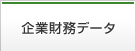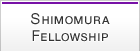シンポジウム・イベント
最近のシンポジウム・イベント等
2024年11月23日(土)、公益社団法人日本不動産学会により、上野 賢一上席主任研究員(現一般社団法人日本電設工業協会所属)、松山将之主任研究員共著『日本におけるESG評価と不動産投資信託の価値関連性についての分析-GRESB評価は、J-REITSの価値を引き上げているのか?-』が「2023年度日本不動産学会賞-論文賞-」に選ばれました。
2024年10月17日(木)に、日本政策投資銀行も協力し、一橋大学CFO教育研究センター主催、TCFDコンソーシアム共催によるシンポジウム「サステナビリティ経営の実践と進化 ~持続的な価値創造のための人財育成~」を開催しました。
基調講演では、キリンホールディングスの藤川常務より、「社会的価値の創造」と「経済的価値の創造」の両立に取り組む当社のCSV経営と、それを支える人財の重要性についてご紹介をいただきました。
また、GX推進機構の梶川理事と一橋大学の伊藤名誉教授との対談セッションでは、政府が進めるグリーントランスフォーメーション(GX)政策と人材育成との関係や、サステナビリティ経営を担う経営人材育成の重要性について、活発な議論が交わされました。
2023年10月3日(火)に、日本政策投資銀行も協力し、一橋大学CFO教育研究センター主催、TCFDコンソーシアム共催によるシンポジウム「サステナビリティ・SX人材の育成と企業価値創造」を開催しました。
日本におけるサステナビリティ経営の現状や、取り組みを持続的な企業価値創造に結び付けていくための課題について、学識者、政策担当者による基調講演が行われたほか、パネルディスカッションには資金提供者や投資家、製造企業からの有識者も加わり、サステナビリティ経営を支える経営人材を育成することの重要性について、活発な議論が行われました。
設備投資研究所は、国際的な学術専門誌 “Global Finance Journal” と連携し、2021年11月11日(木)~12日(金)に、国際カンファレンス/CSR, the Economy and Financial Marketsを開催しました。本カンファレンスは、2017年に当研究所が企画提案し、その後シカゴ(2018年)、デュッセルドルフ(2019年)を経て、このたび第4回目を迎えるに至ったものです。コロナ禍によりオンラインでの開催となりましたが、世界各地の研究者が参加し、CSRと経済・金融を巡る学術研究の報告・討論が活発に行われました。
東京大学金融教育研究センター(CARF)と設備投資研究所は、2021年3月5日(金)に「新型コロナと日本経済~社会科学の視点から」と題した共同シンポジウムを開催いたしました。学識者を中心とする講演やパネルディスカッションを通じ、新型コロナが日本経済に及ぼす影響や今後の展望について、歴史やマクロ経済からの視点のほか、DX・起業・競争政策などにも問題意識を広げて、活発な議論が行われました。
「東京講演会」の概要と開催実績についてご紹介しています。